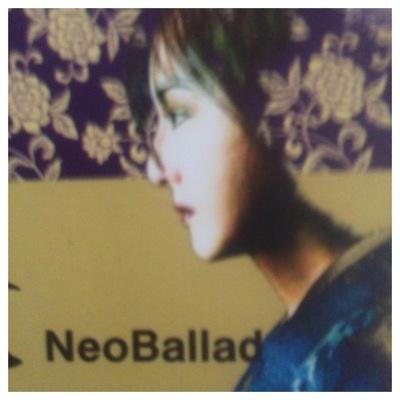
stereotype2085
投稿作品数: 163
総コメント数: 1586
今月は0作品にコメントを付与しました。
総コメント数: 1586
今月は0作品にコメントを付与しました。
プロフィール
記録
プロフィール:
@keisei1さんの現代詩アカ。 stereotype2085として活動しています。どうぞよろしゅうに
@keisei1さんの現代詩アカ。 stereotype2085として活動しています。どうぞよろしゅうに
自作の一押し・・・・
帆を立てて
stereotype2085の記録 ON_B-REVIEW・・・・
ベテラン初コメント送信者
作品への初コメント数バッジ(くわしく)
獲得バッジ数
憧れのレッサー(月毎)
月毎コメント数バッジ(くわしく)
獲得バッジ数
✖0 ✖5 ✖14
奇跡的B-Reviewer
総合コメント数バッジ(くわしく)
獲得バッジ数
投稿者
投稿作品数バッジ(くわしく)
獲得バッジ数